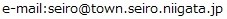「聖籠町手話言語条例」について
 「手話は言語である」という認識に基づき、手話に対する理解や手話を使いやすい環境を整えるために新潟県内で初めての手話言語条例が、平成29年9月22日から施行されました。
「手話は言語である」という認識に基づき、手話に対する理解や手話を使いやすい環境を整えるために新潟県内で初めての手話言語条例が、平成29年9月22日から施行されました。ろう者とろう者以外の人がお互いを尊重し合いながら安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。
条例の概要
- 基本理念
- ・ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重します。
- 町の責務
-
・基本理念に基づき、町民の手話に対する理解を深めます。
・手話の普及と手話を使用しやすい環境の整備を推進します。 - 町民の役割
-
・ろう者と共に生きる地域社会の一員として、手話に対する理解を深めます。
・町が推進する施策への協力に努めます。 - 事業者の役割
-
・ろう者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境整備に努めます。
・町が推進する施策への協力に努めます。 - 施策の推進
- ・「聖籠町障害者計画」に今後どのような事業に取り組んでいくのかを定めます。
条例第15号 聖籠町手話言語条例( PDF:57.0KB )
 手話とは
手話とは手指や体の動き、表情を使って考えや気持ちを視覚的に表現する「目で見ることば」です。
ろう者とは
聞こえに障がいのある人のうち、手話を母語とし、手話でコミュニケーションをとる人たちのことです。